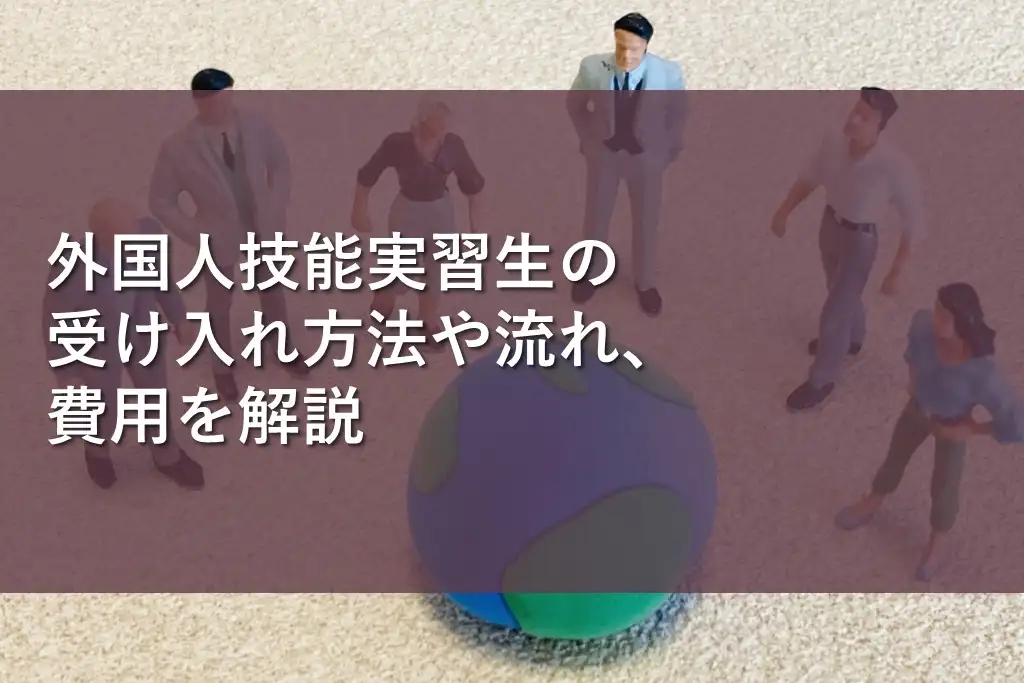
外国人技能実習生の受け入れは、日本企業にとって技術の継承や人材不足の解消など、さまざまなメリットをもたらす可能性があります。
しかし、その受け入れには適切な手続きと準備が必要です。
本記事では、外国人技能実習生の受け入れ方法や流れ、費用について詳しく解説します。
目次
外国人技能実習生を受け入れる方法

外国人技能実習生の受け入れ方法は、主に以下の2つです。
- 団体監理型
- 企業単独型
それぞれの方法について詳しく説明していきます。
特徴や適性を理解し、自社に適した方法を選択しましょう。
団体監理型
団体監理型は、外国人技能実習生の受け入れ方式として一般的な方法です。
2023年末の時点で、この方式による受け入れが全体の98.3%を占めています。
この方式では、営利を目的としない団体が技能実習生を受け入れ、傘下の企業などで技能実習を行います。
営利を目的としない団体とは、事業協同組合や商工会などの非営利団体のことです。
団体監理型は、監理団体が実習生の管理や支援を担当するため、企業の負担が比較的軽減されます。
そのため、特に中小企業に適している受け入れ方法です。
企業単独型
企業単独型は、日本の企業が海外の企業の職員などを直接受け入れ、技能実習を実施する方式です。
2023年末の時点で全体の1.7%と、比較的少ない方法となっています。
企業単独型を選択するためには、以下3つの条件のうち、いずれかに該当する必要があります。
- 企業の範囲が日本の機関の海外にある支店、子会社、合弁会社などである。
- 日本の機関と、引き続き1年以上の国際取引の実績もしくは過去1年間に10億円以上の取引実績がある。
- 日本の機関と国際的な業務上の提携を行っているなど、密接な関わりを持っていると法務大臣および厚生労働大臣が認めている。
企業単独型の強みは、自社の海外拠点や取引先から直接実習生を受け入れられることです。
これにより、自社の業務や文化に馴染みやすい人材を確保できる可能性が高まります。
外国人技能実習生を受け入れる流れ
外国人技能実習生の受け入れには、複数のステップがあります。
各段階で適切な準備と手続きを行うことが、スムーズな受け入れと実習の成功につながるでしょう。
以下では、受け入れの流れを詳細に解説していきます。
職種を確認する
外国人技能実習生の受け入れを検討する際、まず確認すべきは受け入れ可能な職種です。
技能実習制度では、あらゆる職種で実習生の受け入れができるわけではありません。
公益財団法人国際人材協力機構のホームページでは、受け入れ可能な職種が公開されています。
2024年9月30日時点で、91職種167作業が受け入れ可能です。
ここでいう「作業」とは、同じ職種でも使用する機器や製品、現場の違いなどがある場合に職種を細分化したものを指します。
例えば、以下のような職種があります。
- 耕種農業
- 畜産農業
- 漁船漁業
- 鋳造
- 機械加工
- 自動車整備
- 介護
自社の業務に適合する職種があるかどうかを確認することが重要です。
判断が難しい場合は、監理団体に相談するのが賢明でしょう。
適切な職種選択は、実習生の技能向上と企業の期待する成果の両立につながります。
監理団体を選び契約する
監理団体は、技能実習生の募集や受け入れ手続きを行うだけでなく、実習生のサポートやケアも担当します。
そのため、監理団体の選択は、技能実習生の受け入れを成功させるうえで極めて重要です。
監理団体を選ぶ際には、過去の実績やサポートの手厚さなどを考慮しましょう。
確認すべきは、信頼できる団体かどうかです。
監理団体は、労働基準法や技能実習法遵守のために監理・監督する役割を持っています。
適切に対応してくれない監理団体を選んでしまうと、認定取り消しなど、技能実習の運用に悪影響が出る恐れがあるため、慎重に選択しましょう。
送出し国を決定する
外国人技能実習生の受け入れにあたり、送出し国が決められています。
主な送出し国は以下のとおりです。
- インド
- インドネシア
- ウズベキスタン
- カンボジア
- タイ
各国の特徴や状況を理解し、自社の業種や求める人材像に合致する送出し国を選びましょう。
受け入れ人数を確認する
技能実習生の受け入れ人数には上限が設けられています。
以下は団体監理型と企業単独型の人数枠です。
【団体監理型】
| 第1号 | 第2号 | 優良基準適合者 | |||
| 基本人数枠 | 第1号 | 第2号 | 第3号 | ||
| 常勤職員総数 | 技能実習生の人数 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 |
| 301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 | ||||
| 201人~300人 | 15人 | ||||
| 101人~200人 | 10人 | ||||
| 51人~100人 | 6人 | ||||
| 41人~50人 | 5人 | ||||
| 31人~40人 | 4人 | ||||
| 30人以下 | 3人 | ||||
【企業単独型】
| 第1号 | 第2号 | 優良基準適合者 | ||
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | ||
| 常勤職員総数の 20分の1 |
常勤職員総数の 10分の1 |
常勤職員総数の 10分の1 |
常勤職員総数の 5分の1 |
常勤職員総数の 10分の3 |
過度な受け入れは、実習の質低下や管理の困難につながる可能性があります。
これらの上限を念頭に置きつつ、自社の受け入れ体制や指導能力を考慮して、適切な人数を決定しましょう。
求人を提示する
技能実習生を募集する際には、明確な求人条件を提示する必要があります。
この段階で、自社のニーズと実習生の期待のマッチングを図ることが重要です。
求人条件を検討する際は、以下の点に注意しましょう。
- 業務内容:具体的な作業や期待される技能を明記する。
- 勤務条件:労働時間、休日、給与などを明確に示す。
- 必要なスキル:日本語能力や特定の技能の有無など。
- 福利厚生:住居や保険などのサポート内容。
条件が決定したら、送出し国の現地送出し機関に求人票を送って募集をかけます。
以下は、主な送出し国の政府機関名です。
- インド:全国技能開発公社(NSDC)
- インドネシア:労働省(MOM)訓練・生産性開発総局
- ウズベキスタン:雇用・労働関係省(MEHNAT)
- カンボジア:労働・職業訓練省(MLVT)
- タイ:労働省雇用局
各国の送出し機関と連携し、適切な人材の募集を行いましょう。
雇用契約書を作成する
技能実習生との雇用契約書作成は、受け入れプロセスの重要なステップです。
詳細な条件を明記することで、双方の権利と義務を明確にし、トラブルを防ぐことができます。
雇用契約書に記載すべき主な内容は、契約期間や業務内容、労働時間などです。
特に賃金設定は重要で、日本人労働者と同様に最低賃金以上の金額を支払う必要があります。
地域の最低賃金を確認し、適切な賃金設定を行いましょう。
契約書作成の際は、監理団体のスタッフに相談しながら進めると安心です。
彼らの経験と知識を活用し、法的要件を満たす契約書を作成しましょう。
面接・採用を行う
技能実習の候補生が集まったら、次は面接を行います。
面接は、実習生の適性を見極め、相互理解を深める重要な機会です。
面接の方法には、現地面接やオンライン面接の他に、現地の送り出し機関が企業に代わって行う代理面接があります。
面接で確認される事項は、技能実習生としての意欲や適性、日本語能力などです。
また、専門職に関する実技試験を併せて行うこともあります。
採用者が決まったら、事前に作成した雇用契約書に基づいて契約を締結します。
この段階で、双方の期待値を合わせ、スムーズな実習開始につなげましょう。
必要書類を作成する
雇用契約を交わしたあとは、外国人技能実習機構と出入国在留管理庁に必要な書類を提出しなければなりません。
主な必要書類は以下の3つです。
- 技能実習計画認定の申請書
- 査証発給申請書
- 在留資格認定証明書交付の申請書
基本的には監理団体が書類作成やサポートを行ってくれますが、企業側で作成しなければならない書類もある場合があります。
どの書類を自社で準備する必要があるか、監理団体に確認しておくと安心です。
受け入れ体制を整える
技能実習生の配属までに、企業は受け入れ体制を整えておく必要があります。
まず、以下の3つの役職を選任しておくことが法律で定められています。
| 技能実習責任者 | 技能実習の進捗情報を管理する責任者。 |
| 技能実習指導員 | 実習生に直接指導を行う者。 実習生に習得させようとする技能に5年以上の経験が必要。 |
| 生活指導員 | 生活上の指導、生活状況の把握、相談に応じるなど、トラブルを防ぐ役割を担う。 |
これらの役職はすべて、実習を実施する企業に所属する常勤の役員もしくは職員が就かなければなりません。
また、技能実習生の住居の手配も企業の役割です。
住居に関しては以下の点に注意しましょう。
- 1部屋2名以下で、1人あたり4.5平方メートル以上の寝室を確保すること。
- 実習生が受け入れ企業に支払う家賃は2万円まで。
- 敷金礼金などの初期費用は受け入れ側企業が負担する。
また、実習生が日本での生活にスムーズに適応できるように、生活に必要な大型家具、家電、カーテン、布団なども準備しておきましょう。
入国・配属
いよいよ技能実習生が日本に入国する段階です。
しかし、入国後すぐに実習が始まるわけではなく、まずは約1ヵ月間の入国後講習が行われます。
主な学習内容は、日本語や日本で生活するための知識などです。
講習期間中、実習生は通常、講習施設に入寮して集中的に学習を行います。
実習生が日本での生活や仕事に適応するための大切な準備期間です。
入国後講習が終了すると、いよいよ実習生は企業に配属されます。
配属時には、あらためて業務内容や安全管理について丁寧に説明し、実習生が安心して技能修得に取り組めるよう支援しましょう。
外国人技能実習生受け入れにかかる費用
外国人技能実習生の受け入れには、さまざまな費用が発生します。
これらの費用を事前に把握し、適切に予算を組んでおきましょう。
以下に、主な費用項目とその概算を示します。
| 費用項目 | 金額 | |
| 監理団体 | 入会金 | 1〜10万円 |
| 年会費 | 2〜15万円 | |
| 公益財団法人 国際研修協力機構(JITCO) | 年会費 | 10〜30万円 ※JITCOへの入会は必須ではありませんが、さまざまなサポートを受けられるメリットがあります。 |
| 現地事前訪問費用 | 約10万円~25万円 | |
| 技能実習生の入国準備費用 | 在留資格(ビザ)申請 | 約2万円~4万円 |
| 技能実習生総合保険料 | 約2万円~6万円 | |
| 健康診断料 | 約1万円 | |
| 入国前講習費 | 約2万円~4万円 | |
| 入国渡航費 | 約5〜10万円 | |
| 受け入れ後にかかる費用 | 入国後研修費 | 約10万円 |
| 講習手当 | 約6万円 | |
| 雇い入れ健康診断料 | 約1万円 |
これらの費用を合計すると、技能実習生が実習を始めるまでの総費用は、JITCOに入会しない場合で、約42万円~約92万円程度となります。
ただし、JITCOに入会する場合は金額が大きく変わります。
費用が高いということは、それだけ充実したサポート体制が整っていることを意味している場合もあるのです。
そのため、単に費用の安さだけで判断するのではなく、サポートの質や自社のニーズとの適合性を総合的に考慮して選択しましょう。
準備を万全にして外国人技能実習生を受け入れよう
外国人技能実習生の受け入れは、企業にとって大きな機会であると同時に、責任もともなう取り組みです。
適切な準備と体制づくりが、実習生と企業双方にとって有意義な経験につながります。
外国人技能実習生の受け入れは、グローバル人材の育成や国際貢献など、企業にとって多くの価値をもたらす可能性があります。
本記事で解説した受け入れの流れや必要な手続きを参考に、自社の状況に合わせて慎重に計画を立てましょう。






