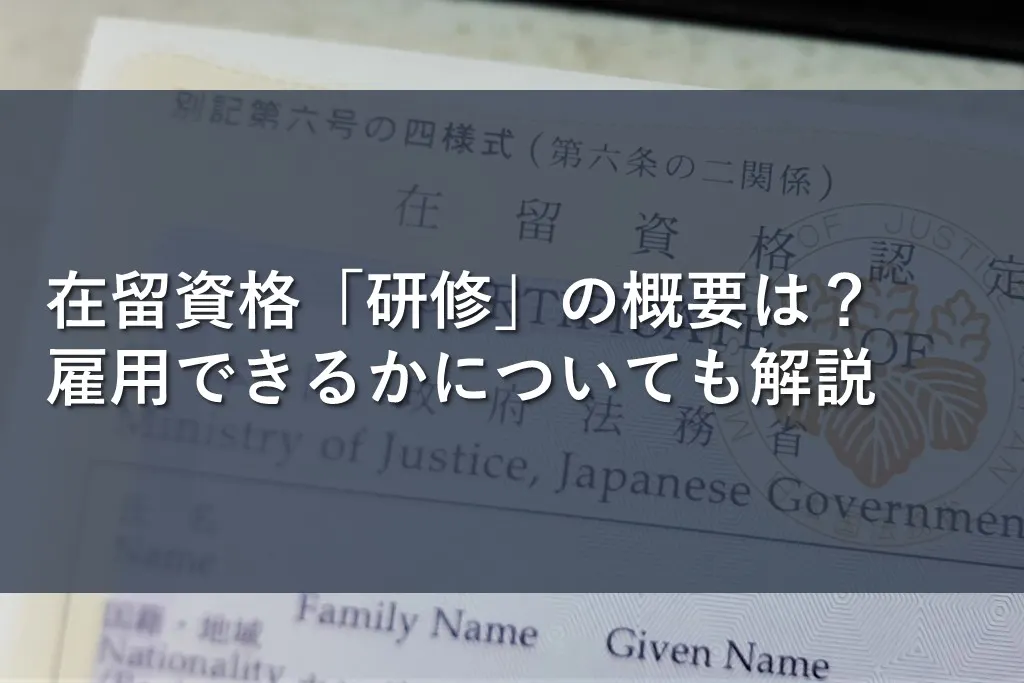
近年、日本の少子高齢化による人手不足のため、国が積極的に外国人労働者を受け入れています。
企業が外国人と雇用契約を結ぶには、当該外国人は雇用されることができる在留資格を持っていることが必須です。
在留資格「研修」とは、日本の公私機関に受け入れられ、技能等の習得活動を行う外国人に与えられる在留資格のことです。
この記事では、在留資格「研修」の概要や取得要件、雇用の可否について詳しく解説します。
目次
在留資格「研修」とは?

在留資格「研修」は、日本の公私の機関で技術や能力を習得することを目的とする外国人に認められる在留資格です。
この資格を持つ外国人は、日本国内での技術・能力の習得をめざす活動が許可されています。
学ぶという点では技能実習生や留学生と似ていますが、その条件は異なります。
最も大きな特徴は、在留資格「研修」の外国人と受入れ機関では、雇用契約を結べないことです。
そのため、給料の支払いは認められておらず、日本での生活に必要な費用のみ受け渡しが可能となっています。
在留資格「研修」の在留期間
在留資格「研修」の在留期間には、1年、6ヵ月、3ヵ月の3種類があります。
最長で1年間の滞在が認められていますが、合理的な理由が認められれば、さらに1年間の延長が可能です。
この柔軟な期間設定により、研修の内容や目的に応じて適切な滞在期間を選択できます。
ただし、延長には十分な理由が必要となるため、当初から研修計画を慎重に立てることが重要です。
在留資格「研修」の取得要件
在留資格「研修」の取得要件は、日本で受ける研修が非実務研修なのか実務研修なのかによって異なります。
それぞれの研修の違いを理解することが、適切な取得要件を満たすための第一歩となるでしょう。
非実務研修と実務研修の違いは、以下のとおりです。
| 研修の種類 | 内容 |
| 非実務研修 | 現場見学や理論学習、日本語教育など、見学や座学、短時間の体験によって修得できる研修 |
| 実務研修 | 商品を実際に生産もしくは販売する業務、対価を得て役務の提供を行う業務に従事し技術を修得する研修 |
非実務研修の場合
非実務研修の場合、取得要件として以下の6つを満たす必要があります。
2. 申請人が18歳以上であり、かつ国籍または住所を有する国に帰国後、日本で修得した技能等を要する業務に従事することが予定されていること
3. 申請人が住所を有する地域において修得することが不可能または困難である技能等を修得しようとすること
4. 申請人が受けようとする研修が、受入れ機関の常勤の職員で、修得しようとする技能等について5年以上の経験を有する者の指導の下に行われること
5. 受入れ機関またはあっせん機関が研修生の帰国旅費の確保、その他の帰国担保措置を講じていること
6. 受入れ機関が研修の実施状況に係る文書を作成し、研修を実施する事業所に備え付け、当該研修の終了の日から1年以上保存するとされていること
これらの要件は、研修の質を保証し、研修生の権利を守るために設定されているものです。
特に、研修生の年齢制限や帰国後の就業予定、指導者の経験などは、研修の効果を高めるために重要な条件となっています。
実務研修を含む場合
実務研修を含む場合は、非実務研修の要件に加えて、追加の要件を満たすことが必要です。
以下のいずれかの追加要件に該当し、さらに状況に応じてその他の要件も満たす場合に限り、在留資格が認められます。
● 申請人が、日本の国もしくは地方公共団体の機関または独立行政法人が自ら実施する研修を受ける場合
● 申請人が独立行政法人国際観光振興機構の事業として行われる研修を受ける場合
● 申請人が独立行政法人国際協力機構の事業として行われる研修を受ける場合
● 申請人が独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構石油開発技術センターの事業として行われる研修を受ける場合
● 申請人が国際機関の事業として行われる研修を受ける場合
● 日本の国、地方公共団体等の資金により主として運営される事業として行われる研修で、受入れ機関が以下のすべてに該当する場合
○ 研修生用の宿泊施設および研修施設を確保していること
○ 生活指導員を置いていること
○ 研修生の死亡、疾病等に対応する保険への加入などの保障措置を講じていること
○ 研修施設について安全衛生上の措置を講じていること
● 外国の国、地方公共団体等の常勤の職員を受け入れて行われる研修の場合は、受入れ機関が上記その他の要件のすべてに該当していること
● 外国の国、地方公共団体に指名された者が、日本の国の援助および指導を受けて行われる研修で、以下のすべてに該当する場合
○ 申請人が住所地において技能等を広く普及する業務に従事していること
○ 受入れ機関が上記その他要件すべてに該当していること
これらの要件は、実務研修の質と安全性を確保するために設定されています。
特に、公的機関や国際機関が関与する研修に限定されている点や、受入れ機関の設備や体制に関する詳細な条件は、研修生の保護と研修の効果を最大化するための重要な基準です。
在留資格「研修」で雇用できる?
在留資格「研修」で外国人労働者を雇用することはできません。
この在留資格では、雇用契約を結ぶことが認められていないのです。
通常、就労が認められていない在留資格でも、資格外活動許可を取得すれば条件付きで就労できる場合があります。
しかし、在留資格「研修」は資格外活動の対象外となっています。
これは、生活費が受入れ機関から支給されるため、アルバイトなどで生活費を稼ぐ必要がないからです。
在留資格「研修」は雇用できない
在留資格「研修」は、雇用契約を結ぶことができません。
外国人が日本で技術や能力を習得することのみを目的としているからです。
研修生は、給与ではなく生活に必要な費用のみを受け取ることができます。
また、資格外活動も認められていないため、アルバイトなどの副業もできません。
このような制度設計により、在留資格「研修」で日本に滞在する外国人には、純粋に技術習得を目的とした活動のみが認められています。
雇用を目的とした在留資格ではないため、企業が労働力として研修生を受け入れることはできません。
研修生を受け入れる機関は、適切な研修環境の提供と生活サポートを行う責任があります。
受け入れを検討する際は、雇用ではなく教育的な観点からアプローチする必要があるのです。






