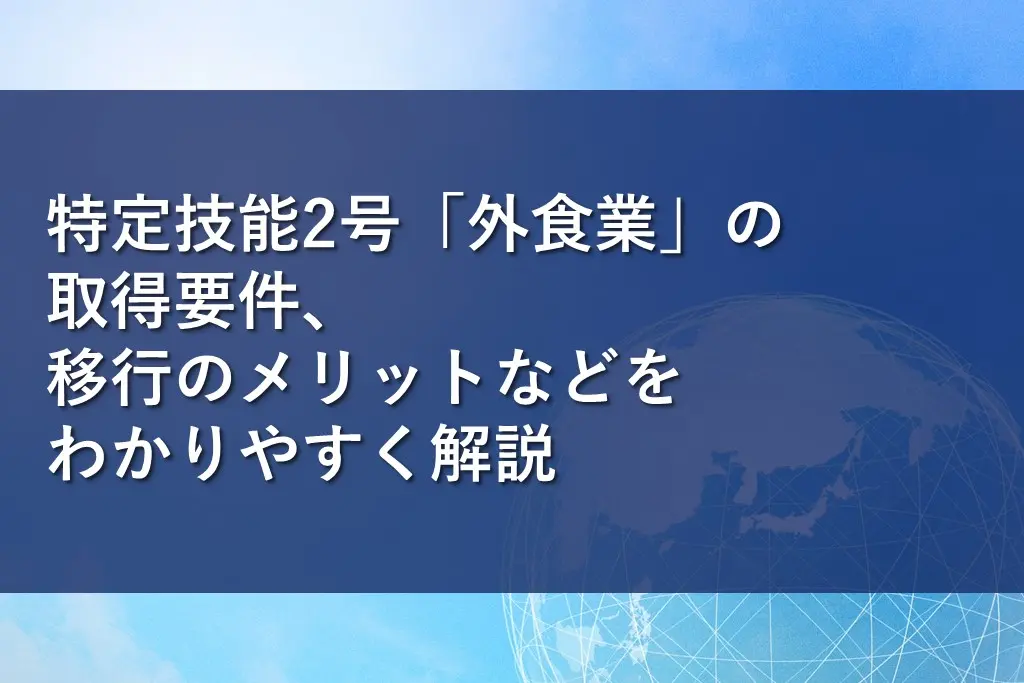
日本の深刻な人手不足を補うために作られた特定技能制度は、外国人労働者の受入れを拡大するための在留資格の一つです。
特に、令和5年に新設された特定技能2号「外食業」では、レストランのホール業務からラーメン店の調理スタッフまで、幅広い外食業とその関連業務で働くことができます。
この記事では、特定技能2号「外食業」の取得要件や、1号から2号への移行のメリットについて詳しく解説していきます。
目次
「外食業」の特定技能2号を取得するための要件

特定技能2号を取得するためには、試験の合格と実務経験の両方が必要となります。
ここでは、それぞれの要件を詳しく見ていきましょう。
必要な試験
外国籍の方が特定技能2号「外食業」を申請するには、「外食業特定技能2号技能測定試験」と「日本語能力試験(N3以上)」の両方に合格することが求められます。(一部のケースでは免除あり)
外食業特定技能2号技能測定試験では、接客全般、飲食物調理、衛生管理、店舗運営に関する知識が求められます。
試験対策として、外食業技能測定試験学習用テキストなどを配布している協会もあるので、活用すると良いでしょう。
一方、日本語能力試験は、日本語を母国語としない人の日本語能力を測定するための試験で、国際交流基金と日本国際教育支援協会によって実施されています。
N3以上の合格が求められる特定技能2号「外食業」では、日常的な場面で使われる日本語をある程度理解できることが必要とされています。
必要な実務経験
特定技能2号を取得するためには、外食業特定技能2号の技能測定試験の合格、日本語能力試験N3以上の合格に加えて、食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業許可を受けた飲食店での2年間の実務経験が必要です。
この実務経験では、複数のアルバイトや特定技能外国人の指導・監督をしながら接客業務を行いつつ、副店長やサブマネージャーとして店舗管理の補助を担当した経験が求められます。
つまり、単に店舗で勤務するだけではなく、管理業務に携わった経験も求められるのです。
必要な申請書類
特定技能2号「外食業」の申請にあたり、全分野に共通の書類とは別に必要な書類は以下のとおりです。
- 外食業特定技能2号技能測定試験の合格証明書の写し
- 日本語能力試験(N3以上)の合格証明書の写し
- 保健所長の営業許可証または届出書の写し
- 外食業分野での特定技能外国人の受入れに関する誓約書
- 協議会の構成員であることの証明書(特定技能外国人の初回の受入れから4ヵ月以上経過している場合)
- 指導等実務経験証明書等(外食業)
これらの書類を揃えて申請することで、特定技能2号「外食業」の在留資格を取得できます。
「外食業」で特定技能2号へ移行するメリット
特定技能1号から2号へ移行することには、いくつかのメリットがあります。
まず、在留期間の上限が撤廃されます。
1号の在留期間は最長5年ですが、2号では上限がなく、3年、1年、6ヵ月ごとの更新が可能です。
ただし、許可される在留期間は審査官の判断になるため、申請時の希望どおりになるとは限りません。
また、要件を満たせば家族の帯同も可能です。
家族帯同が認められていない特定技能1号に比べて安心して働き続けられるため、定着率の向上につながる可能性があります。
仕事内容も大きく変わります。
2号になると、1号の仕事に加えて外食業全般の業務について店舗をトータルで管理できるようになるため、店舗の経営分析や管理、契約に関する事務を担える可能性が広がるのです。
さらに、受入れ企業側のメリットとして、支援計画を策定・実施する必要がないため、特定技能1号に比べて育成のコスト負担が軽くなる点が挙げられます。
「外食業」の特定技能の取得状況
外食業の特定技能2号は、令和5年6月に閣議決定された新しい制度です。
令和5年12月末時点で、特定技能1号の外国人労働者は1万3千人以上いましたが、2号の取得者はいませんでした。
しかし、令和6年3月に行われた外食業特定技能2号技能測定試験の国内試験では、292人が受験し、113人が合格しています。
今後、特定技能2号の取得者が増えていくことが期待されています。
特定技能2号「外食業」により人手不足の解消が期待できる
特定技能2号「外食業」は、深刻な人手不足に悩む外食業界にとって、外国人労働者の受入れを拡大するための重要な制度です。
取得にはいくつかの要件がありますが、1号から2号へ移行することで、在留期間の上限撤廃や家族の帯同、仕事内容の拡大といったメリットが得られます。
現在、特定技能2号の取得者はまだ少ないですが、今後増加していくことが予想されます。
特定技能2号「外食業」が、外食業界の人手不足解消と外国人労働者の活躍につながるでしょう。







