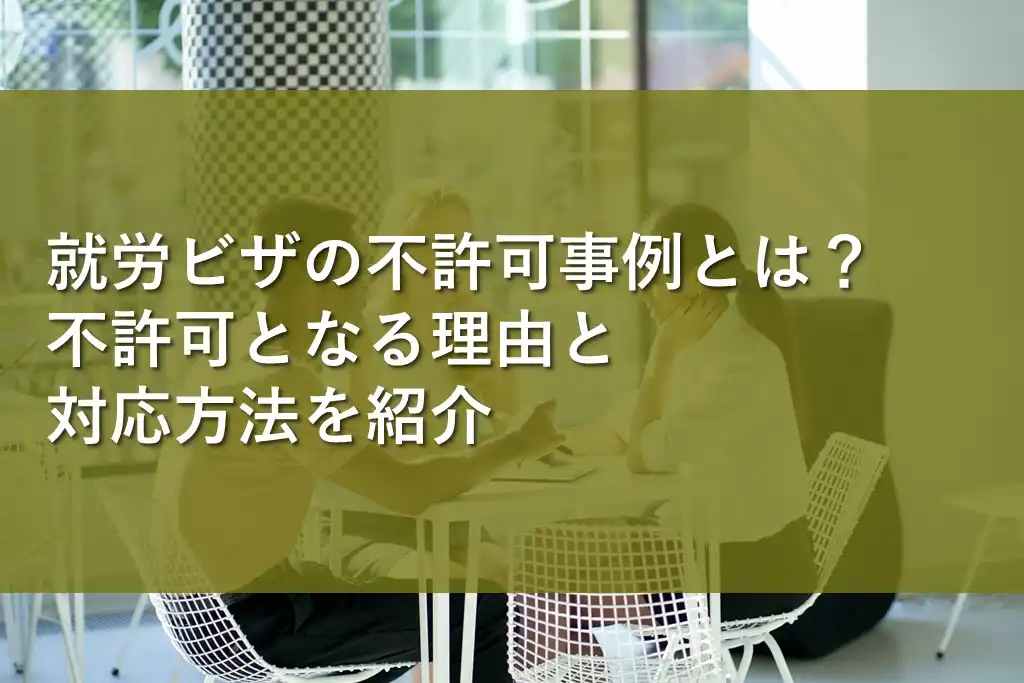
外国人労働者の雇用を検討する企業にとって、就労ビザの取得は重要な課題です。
しかし、就労ビザの申請が不許可になるケースもあります。
不許可となる理由や事例を知り、適切な対策を講じることが必要です。
本記事では、就労ビザが不許可になる事例や対応方法、企業が注意すべきポイントについて解説します。
目次
就労ビザの不許可事例

就労ビザの申請が不許可となるケースには、いくつかの共通した理由があります。
ここでは、代表的な不許可事例について見ていきましょう。
外国人の専攻科目と職務内容に関連性がない
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、就労ビザで不許可になった事例が公表されています。
そのなかに、外国人労働者の専門科目と職務内容に関連性がないことが挙げられています。
例えば、経済学部出身の外国人から会計事務に従事するための在留資格の申請があったものの、就職先が料理店であり、業務内容の説明を求めても明確な返答が得られなかったというケースです。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する仕事内容と認められず、不許可になりました。
外国人労働者の専門性と職務内容との関連性が、重要であることがわかります。
業務が在留資格に該当していない
外国人労働者の仕事内容が在留資格で認められている活動の範囲外である場合も、不許可となるケースがあります。
例えば飲食店で働く場合、「技能」の在留資格でホールや皿洗いの仕事をする場合は、従事する仕事内容が在留資格と合っていないとして不許可となります。
在留資格と業務内容の整合性が必要です。
雇用する企業側に問題がある
雇用する企業側に問題があるケースも、不許可となる場合があります。
例えば、企業の決算から正社員雇用の可能性が少ないと判断された場合や、外国人労働者に対して最低賃金よりも低い金額を提示した場合、会社の規模が非常に小さい場合など、外国人労働者を安定して雇用できる能力がないと判断された場合は不許可となります。
企業の雇用能力も審査の対象となるのです。
外国人労働者本人に問題がある
外国人労働者が在留中に問題を起こしてしまったケースも、不許可となる場合があります。
具体的には、出入国在留管理局とのトラブルや、入管法違反を犯していたケースです。
また、在留資格を留学から就労ビザに変更する際に、資格外活動上限制限違反をしたケースや、留学している学校の出席状況が悪いケースも不許可となる可能性があります。
外国人労働者自身の在留状況も、就労ビザ審査の重要なポイントなのです。
就労ビザが不許可になったときの対応
就労ビザが不許可になったからといって、諦める必要はありません。
不許可理由を把握し、適切に対応することで、再申請への扉が開かれます。
不許可となった理由を把握する
就労ビザの申請が不許可になった際は、まず不許可となった理由を把握することが大切です。
不許可となった理由によっては、その理由に対応したうえでの再申請が可能となります。
不許可と判断された場合は、不交付理由が記載された不交付通知書または入管への来庁を要請する通知書が届きます。
詳細な不許可理由を知るには、入管に直接理由を聴きに行くことが必要です。
理由説明は一度しか実施されず、専門的な用語が使用される可能性があるため、可能な限り外国人労働者だけでなく企業担当者も同行すると良いでしょう。
不許可理由を正確に理解することが、再申請の第一歩となります。
就労ビザを再申請する
不許可理由を解消できる手段があれば、就労ビザを再申請しましょう。
例えば、外国人の専門科目と仕事内容に関連がなく不許可となったケースであれば、企業側で業務内容を変更し、関連性を証明できれば、再度就労ビザを申請できます。
不許可理由に応じた適切な対応を取ることで、再申請の道が開けるのです。
就労ビザの不許可事案を起こさないために企業が注意すべきこと
就労ビザの不許可事案を避けるためには、企業側の事前の確認と対策が重要です。
ここでは、企業が注意すべきポイントを見ていきましょう。
学歴・仕事内容を確認する
就労ビザ申請前に、外国人の学歴や職歴と、自社での仕事内容に関連性があるかを確認することが大切です。
外国人から口頭で確認するだけではなく、卒業証明書などで確認しておくと安心でしょう。
企業側が外国人労働者に与えるポジションによっても、学歴と仕事内容を合わせることが可能です。
どのようなポジションで活躍してもらうか、相手のスキルを把握して適切に配置できるよう、企業側でも工夫する必要があります。
外国人労働者の専門性を活かせる職務内容を用意することが重要なのです。
在留資格・仕事内容を確認する
学歴や職歴だけでなく、申請する在留資格と自社での仕事内容が合っているかも確認する必要があります。
同じ接客の仕事であっても、ホール専属のスタッフとして採用するのか、それとも総合職として採用するのかによって、活用できる在留資格が異なります。
在留資格の範囲内で、外国人労働者の能力を最大限に発揮できる仕事内容を検討しましょう。
在留資格と業務内容のミスマッチを防ぐことが、就労ビザ取得の鍵となります。
就労時間を調整する
日本の労働基準法では、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)が定められています。外国人労働者がこれを大幅に超える長時間労働を強いられる場合や、適切な割増賃金が支払われていない場合、違法とみなされる可能性があります。
なお、資格外活動許可を取得した留学生を雇用する場合は、規定の就労時間を超えないように調整することが求められます。
留学生の場合は、週28時間以内を上限としてアルバイトなどの資格外活動を行うことができます。
しかし、上限の時間を超えてしまうことによって、在留資格の更新・変更が不許可になる恐れがあるのです。
留学生は就労時間を適切に管理し、規定の範囲内で働いてもらうことが特に大切です。
就労時間の調整は、留学生の在留資格維持のためにも欠かせない対策となります。
就労ビザの不許可事例を知って事前に対策を立てよう
就労ビザの不許可事例を知ることで、企業は事前に対策を立てることができます。
外国人労働者の専門性と職務内容の関連性、在留資格と仕事内容の整合性、企業の雇用能力、外国人労働者本人の在留状況などを確認し、問題がある場合は改善することが重要です。
不許可になった場合でも、理由を把握し適切に対応することで、再申請の可能性が広がります。
就労ビザの不許可事例を参考に、外国人労働者の雇用を円滑に進めていきましょう。






