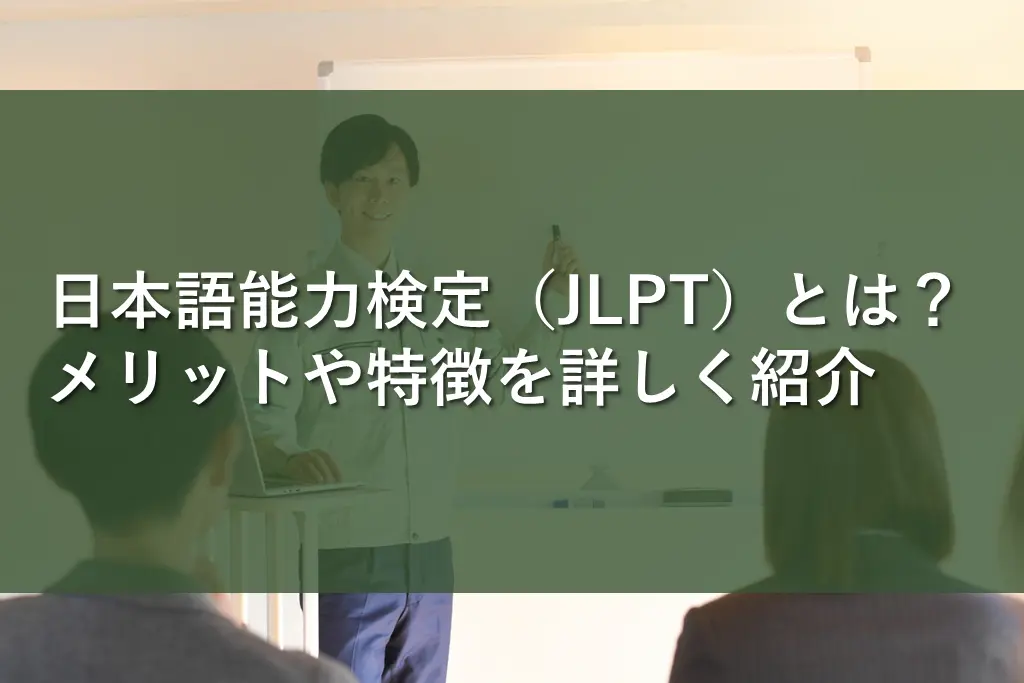
日本語能力検定は正式には日本語能力試験(JLPT)といい、日本語を母語としない人を対象とした、日本語能力を測定するための世界的な指標です。
日本国内だけでなく世界各国で実施されており、合格すれば日本の大学への留学や就職など、さまざまな道が開かれるでしょう。
また、外国人の方が日本語を学ぶなかで、自分の日本語能力を客観的に評価することも可能です。
本記事では、日本語能力試験の目的や特徴、合格のメリットなどを解説します。
目次
日本語能力検定(JLPT)とは
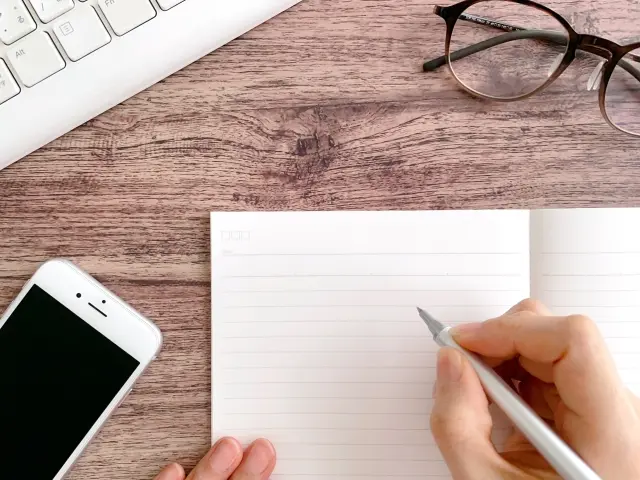 日本語能力検定の正式名称は、日本語能力試験(JLPT)といいます。
日本語能力検定の正式名称は、日本語能力試験(JLPT)といいます。
日本語能力試験は、日本語以外の言葉を母語とする人を対象に、日本語能力を測定し認定するための試験です。
日本語の習得度を評価する世界的な基準となっており、2023年には126万人以上が受験しました。
まずは、日本語能力試験の目的や特徴を詳しく見てみましょう。
日本語能力試験の目的
日本語能力試験は、国際交流基金と日本国際教育協会により1984年から開始されました。
原則、母国語が日本語ではない人を対象に、その日本語能力を測ることを目的とした試験です。
発足当初の受験者数は全世界で7,000人程度ほどでしたが、2023年には受験者数126万5,435人と、世界最大規模の日本語試験となりました。
試験は世界中で年に2回、7月と12月に実施されます。
日本語能力試験によって日本語の能力が認められると、在留資格の認定や就職、昇給・昇格などさまざまな場面で活用できるでしょう。
日本語能力試験の特徴
日本語能力試験には、以下4つの特徴があります。
- コミュニケーション能力のチェック
- 5段階のレベルから自分に合ったレベルを選べる
- 尺度得点を導入している
- レベル別にCan‐doリストが提供される
試験は5段階のレベルに分けられており、日本語の語彙力や文法はもちろんのこと、コミュニケーションスキルなども測定が可能です。
コミュニケーション能力のチェック
日本語能力試験では、日本語の文字や語彙、文法をどのくらい知っているかだけではなく、その知識を利用してコミュニケーション上の課題を遂行できるスキルも試されます。
日常生活や仕事をするなかで言語上の課題を解決するには、状況に合わせて日本語の知識を活用する力も重要になるためです。
試験は言語知識(文字・語彙・文法)と読解、聴解の3つから構成されており、選択肢を選ぶマークシート方式で行われます。
試験官と直接話すような面接試験は実施されませんが、総合的な科目構成からコミュニケーション能力を測ることが可能です。
5段階のレベルから自分に合ったレベルを選べる
日本語能力試験には、N1・N2・N3・N4・N5の5段階のレベルがあり、自分のレベルに合った試験を受けられます。
N1が最も難しく、N5が最もやさしい難易度です。
比較的やさしい難易度のN4とN5では基本的な日本語の理解度を測るのに対し、N3ではより日常的な場面で使われる日本語の理解度をチェックします。
N2とN1では、日常的な場面で頻出する日本語に加えて、さらに幅広い場面で使われているやや複雑な日本語の理解度も測定されるのが特徴です。
尺度得点を導入している
試験の難易度は毎回多少変動するため、同じ能力を持つ人でも試験内容によって得点が違ってしまう可能性があります。
よって日本語能力試験では、より公平なものさしで得点を割り出す尺度得点という得点方式を採用しているのが特徴です。
尺度得点であれば、試験の難易度に関わらずいつでも同じ基準で日本語能力を測定できるため、受験年度が違っていても公平性が保たれます。
レベル別Can-doリストが提供される
「日本語能力試験合格者と専門家の評価によるレベル別Can-doリスト」は、各レベルの合格者が日本語スキルを使ってどのようなことができるのかをまとめた資料です。
このリストは、受験者の自己評価調査に基づいて統計的に分析し作成されました。
各レベルの合格者のうち「できる」あるいは「なんとかできる」の回答率が75%を超えたものを、そのレベルの日本語能力者ができることとしてリストに提示しています。
注意点として、日本語能力試験の出題基準ではないため、これを参考に勉強したとしても、合格者の日本語能力を保証するものではないことを理解しておきましょう。
出題基準は、日本語能力試験ホームページから認定の目安や問題例、ガイドブックなどを確認するようにしてみてください。
日本語能力試験のメリット
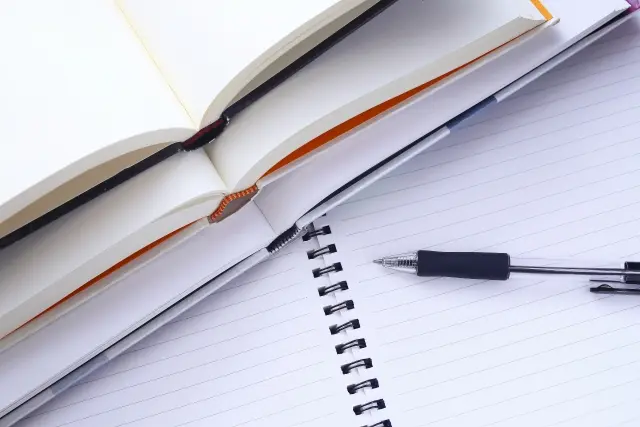
日本語能力試験の合格には、大きく4つのメリットがあります。
- 出国管理上の優遇措置を受けるためのポイントが付与される
- 一部国家試験を受けるための条件の一つ
- 中学校卒業程度認定試験で国語の試験科目免除
- 看護師・介護福祉士の候補者選定条件の一つ
順に詳しく見てみましょう。
出国管理上の優遇措置を受けるためのポイントが付与される
「高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度」では、日本語能力試験N1の合格者には15点、N2合格者には10点が付与されます。
特別高度人材制度は、学歴や職歴、年収などが一定以上の水準を満たした外国人労働者の方を日本企業で受け入れるための制度です。
人材を受け入れるにあたって、こうした水準のほかに、高度人材ポイントの合計が70点以上となった方は出入国管理上の優遇措置を受けられます。
例えば「高度専門職1号」の場合、複数の在留資格にまたがる活動が行えるほか、5年の在留期間を付与してもらうことが可能です。
一部国家試験を受けるための条件の一つ
海外で医師免許などを持っている人が、日本で同じ職種の国家試験を受験するためには、日本語能力検定N1の認定が必要です。
日本語能力検定N1が受験資格となっている国家試験には、次のようなものが挙げられます。
- 医師
- 歯科医師
- 獣医師
- 看護師
- 薬剤師
- 歯科衛生士
- 臨床検査技師
- 作業療法士
- 救命救急士 など
例えば医師国家試験受験資格認定は、医学校で6年以上学んだ海外の医師免許を持つ人が日本語能力試験N1に合格した場合、受験資格を得られます(医学校卒業から10年以内)。
日本で医療従事者として働くためには、高い日本語能力が求められるといえるでしょう。
中学校卒業程度認定試験で国語の試験科目免除
日本語能力検定N1またはN2に合格していると、日本の中学校卒業程度認定試験を受験する際に、国語の試験が免除されます。
やむを得ない事情で中学校に通えない、あるいは免除された満15歳の方が卒業認定を受けたい場合、国語・数学・理科・社会・外国語の5教科の試験を受験しなければなりません。
合格により、高等学校への入学資格を得られます。
ただし、日本語能力検定N1もしくはN2に認定された外国籍の方などは、国語の試験を受ける必要がありません。
看護師・介護福祉士の候補者選定条件の一つ
EPA(経済連携協定)に基づいて、インドネシア、フィリピン、ベトナムから来日する看護師や介護福祉士の候補者は、日本語能力試験による認定が必要です。
インドネシア、フィリピンの方であればN4程度、ベトナムの方ならN3以上が求められます。
通常、看護師や介護福祉士の候補者は来日前に日本語の研修を受けますが、日本語能力試験N2以上に合格している方は研修の免除対象です。
インドネシア、フィリピンの方に関しては、訪日後の研修も同様に免除となります。
N3~N4以上に認定されなければ、日本への入国自体が許可されない可能性もあるため注意が必要です。
日本語能力試験の受験は、看護師や介護福祉士の方が日本で働くための重要な条件の一つといえるでしょう。
日本語能力検定の難易度解説
日本語能力試験のレベル認定の目安は、「読む」「聞く」という言語行動で表されます。
これらの言語行動には、文字への理解をはじめ語彙や文法などの言語知識が必要不可欠です。
上述したとおり、日本語能力試験にはN1・N2・N3・N4・N5の5つのレベルがあり、N1が一番難しくなっています。
| レベル | 難易度の目安 |
|---|---|
| N5 | 基礎レベルの日本語をある程度理解できる |
| N4 | 基礎レベルの日本語を使いこなせる |
| N3 | 日常的な日本語をある程度理解できる |
| N2 | 日常的な日本語を使いこなせるとともに、幅広い場面で使われる日本語も多少理解できる |
| N1 | 日常会話からあまり馴染みのない話題まで、幅広い場面で使われる日本語が理解できる |
ここからは、各レベルの難易度をより具体的に解説します。
N5の難易度解説
N5の認定目安は、基本的な日本語をある程度理解できることです。
日本語を読む能力としては、ひらがなやカタカナ、日常生活でよく使われる基礎的な漢字で書かれた文章を読んで内容を把握する力が求められます。
聞く能力では、学校や職場などでよく遭遇するような日常的な場面でゆっくりと話される短い会話なら、必要な情報を聞き取れる程度が目安です。
簡単な指示を受けて行動するほか、自己紹介や基本的な挨拶ができるレベルといえます。
N4の難易度解説
N4の認定目安は、基本的な日本語を十分に理解できることです。
読む能力では、基礎レベルの語彙や漢字を使って書かれた日常的で身近な話題の文章を読み、内容を把握できる力が求められます。
聞く能力では、ややゆっくりと話される日常会話であれば、内容がほとんど理解できる程度が目安です。
趣味や週末の予定などについて話す、職場の掲示板の内容を理解して行動する、伝達事項をメモに残すといったこともできるようになります。
N3の難易度解説
N3の認定目安は、日常的な日本語をある程度理解できることです。
読む能力では、身近な話題について書かれた文章を読み内容を把握できるほか、新聞や資料の見出しから情報の要点をつかむスキルなども求められます。
また、N3合格者であれば、日常的な場面のうちやや難易度が高いシチュエーションでも、簡単な表現に言い換えて伝えてもらえれば、要旨を理解できるようになるでしょう。
聞く能力では、ほとんど自然に近いスピードで日常会話を聞いても、話の内容を問題なく理解できる程度が求められます。
N2の難易度解説
N2の認定目安は、日常会話の理解に加えて、より幅広いシチュエーションで使われる日本語も多少理解できることです。
読む能力では、新聞や雑誌の記事、簡単な評論など、趣旨がわかりやすい文章を読んで内容を把握する力が求められます。
身近な話題に関する文章であれば、話の流れや表現の意図も理解できるようになるでしょう。
聞く能力では、日常生活から学校、職場、馴染みのない話題まで、幅広い場面で自然に近いスピードの日本語を聞き、話の流れや登場人物の関係を理解できる力が求められます。
N1の難易度解説
N1の認定目安は、幅広い場面で使われる日本語を理解できることです。
読む能力では、評論文のようなやや複雑な文章を読んで、構成や内容を理解できる力が求められます。
N1合格者であれば、政治・経済など人によってはあまり身近でない話題の読み物であっても、話の流れや詳細な表現意図を理解できるようになるでしょう。
聞く能力でも同様に、幅広い場面で自然なスピードの会話やニュースなどを聞き、話の流れや要点、登場人物の関係などを把握できる程度のレベルが求められます。
自分自身の意見と集めた情報をもとに、レポートなどにまとめることも可能です。
日本語能力検定の取得で就学・就労に活かせる
日本語能力試験は、日本語を母国語としない人が日本語能力を測定するための試験です。
試験にはN1からN5までの5段階のレベルがあり、自分のレベルに合った内容で受験できます。
日本語の文法や語彙などの基礎知識だけでなく、その知識を使ってコミュニケーション上の課題を遂行できるかどうかを、読む力・聞く力から問われるのが特徴です。
合格した方は日本での就職や進学で有利になったり、出入国管理上の優遇措置を受けるためのポイントが付与されたりなど、さまざまなメリットを得られます。
また、外国人材を受け入れたい企業にとっても、日本語能力試験は採用活動を行う際の一つの判断材料となるでしょう。
N1、N2合格者は日本語スキルが高い反面、獲得のハードルが上がるため、自社の人員配置の状況や任せたい業務に合わせて適切な採用基準を設けるようにしてみてください。






