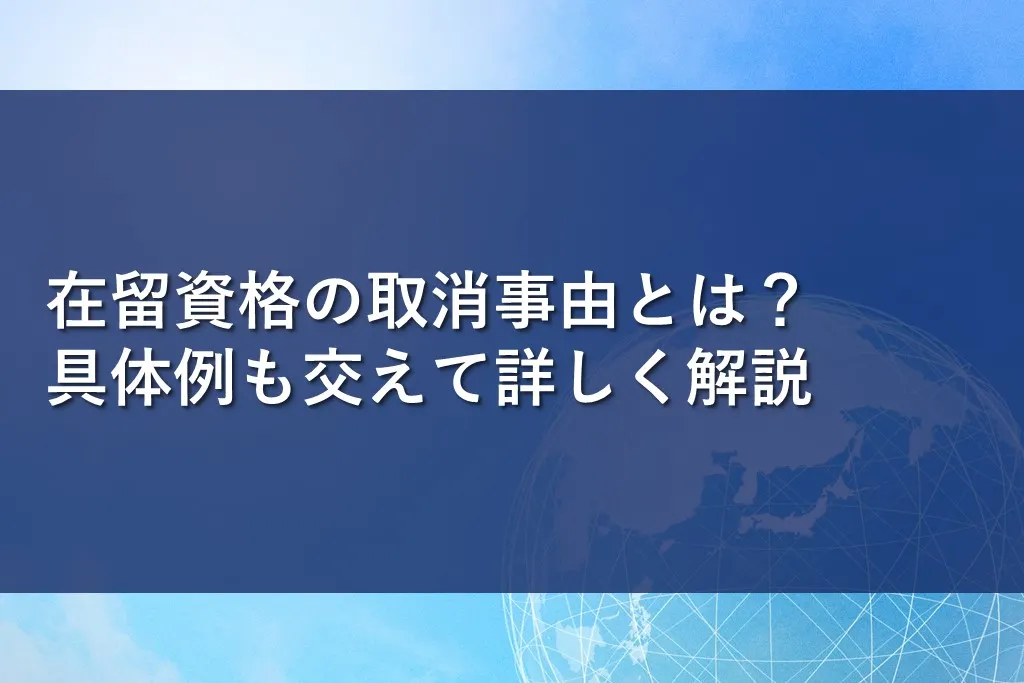
在留資格の取消しは、日本に滞在する外国人の生活に大きな影響を与える事態です。
外国人本人に違法行為の自覚があった場合だけでなく、悪意なく法律に違反してしまった場合でも、在留資格の取消事由に該当する可能性があります。
在留資格の取消し件数は近年増加傾向にあり、外国人を雇用する企業にとっても無視できない問題といえるでしょう。
本記事では、在留資格の取消事由の概要や具体的な事例を紹介するとともに、受け入れ企業としてどのように対応すべきかを解説します。
違法性の高い人材を就労させた場合、企業も罪に問われるリスクがあるため、適切な外国人雇用のために理解を深めておくことが大切です。
目次
在留資格の取消事由とは

在留資格の取消事由とは、該当した場合に在留資格を取消す対象であると判断される事柄のことです。
在留資格の取消は、出入国管理及び難民認定法(入管法)に定められた制度であり、不法行為が発覚した外国人は、在留資格の取り消し処分を下されます。
法務大臣は、日本に滞在する外国人に在留資格取消事由に該当する疑いがある場合、意見聴取などで事実を確認したうえで、その資格を取り消すことが可能です。
出入国在留管理庁によれば、2023年の在留資格の取消し件数は1,240件で、前年2022年の1,125件と比較すると10.2%増加し、過去最多となりました。
在留資格を得て日本で生活を送る外国人が増えると同時に、取消事由に該当するケースも多発しており、外国人の受け入れ企業でも十分な注意が必要です。
雇用管理が適切でなければ、自社で働いている外国人の在留資格が取り消されるだけでなく、受け入れ企業も法的責任を問われるリスクがあります。
企業側でも在留資格の取消事由について正しく理解し、違法性のない安全な雇用管理を徹底しましょう。
在留資格の取消事由と判断される理由
在留資格の取消事由は、大きく3つのカテゴリに分類されます。
- 犯罪などによる上陸拒否該当者であるにも関わらず、虚偽の書類を提出して事実を偽り入国した場合
- 在留資格に該当する活動を行っていない場合
- 中長期滞在者が虚偽の居住地を届け出ている、または90日以内に居住地を届け出ていない場合
具体的には、次のような事実が判明した場合、入管法の第22条の4第1項の規定によって、法務大臣は該当外国人の在留資格を取り消せます。
- 不正手段により入国審査官の誤判断を招き上陸許可を受けた場合
- 日本で行う活動内容や経歴を偽って入国した場合
- 上記以外で、虚偽の書類を提出し上陸許可を受けた場合
- 偽りなど不正な手段により在留特別許可を受けた場合
- 在留資格に該当しない活動を行った場合、または行おうとして在留している場合
- 在留資格に定められた活動を継続して3ヵ月行っていない場合
- 日本人または特別永住権の配偶者として在留資格を持つ外国人が、配偶者としての活動を6ヵ月継続して行っていない場合
- 上陸許可や在留資格変更によって中長期滞在を認められた外国人が、90日以内に出入国在留管理庁長官へ居住地の届出をしなかった場合
- 引越しをした外国人が、90日以内に出入国在留管理庁長官へ新しい居住地の届出をしなかった場合
- 中長期在留者が出入国在留管理庁長官へ虚偽の居住地を届け出た場合
受け入れ企業は、外国人の採用時だけでなく雇用が開始してからも、定期的に在留資格の取消事由に該当していないか確認することが大切です。
在留資格が取消しされたらどうなる?
外国人の在留資格が取り消されたあとの処分は、事由によって異なりますが、大きく以下2パターンに分けられます。
- 不正手段や虚偽の活動内容・経歴を申告して取り消された場合
この場合、外国人は退去強制命令の対象です。
即座に日本を出国しなければならず、再入国も困難になる可能性が高くなります。 - それ以外の事由の場合
出国のための期間(最大30日)が指定され、外国人はこの期間内で自主的に出国しなければなりません。
ただし、在留資格に該当する活動を行わずに取消しとなった場合で、外国人本人が逃亡する可能性があるときには、すぐさま退去強制の対象となることがあります。
在留資格が取り消された外国人は、日本で就労できなくなるばかりか、滞在も認められません。
よって外国人本人だけの問題ではなく、受け入れ企業にも大きな影響を与えるでしょう。
在留資格の取消しの手続き
在留資格の取消しは、以下の手続きを経て進められます。
- 在留資格の取消事由に該当する疑いのある外国人を特定
- 入国審査官または入国警備官が事実の調査
- 意見聴取
- 法務大臣(または委任を受けた出入国在留管理庁長官および地方出入国在留管理局長を含む)が取消しを判断
手続きの過程では、該当する外国人に弁明の機会が与えられるのが一般的です。
在留資格の取消しが決定すると、事由に応じて退去強制や出国までの猶予期間の設定などが進められます。
雇用している外国人に疑いがかけられた場合、専門家へ速やかに相談するなどして、企業側でも適切な対応を取ることが重要です。
また、外国人本人ともきちんと話し合う時間を設け、状況を正確に把握しましょう。
在留資格の取消事由に該当しうる事例

在留資格の取消事由に該当しうる外国人の事例を、より詳しく解説します。
思わぬトラブルに巻き込まれないために、受け入れ企業でも外国人の在留資格で定められた活動内容を正しく認識しておきましょう。
日本人または特別永住者の配偶者として活動していない場合
日本人または永住者の配偶者の在留資格を持つ外国人が、離婚などを機に配偶者としての活動を一定期間以上行っていない場合、在留資格取消事由に該当する可能性があります。
例えば、次のようなケースです。
- 離婚後6ヵ月が経過しても、新しい在留資格への変更手続きを行わず日本に滞在している場合
- 配偶者の死亡後6ヵ月が経過しても、新しい在留資格への変更手続きを行わず日本に滞在している場合
- 日本人や永住者との婚姻関係が偽造結婚であった場合
これらの状況は「在留資格に該当する活動を行っていない」と見なされますが、正当な理由があれば取消しの対象とはなりません。
日本人や永住者の配偶者などの在留資格を持つ外国人を雇用している企業では、状況に応じて適切なアドバイスや支援を実施する必要があるでしょう。
留学生が学校の授業を欠席している場合
留学の在留資格を持っていながら、学校の授業を頻繁に欠席している外国人も、本来の在留資格に該当する活動を行っていないと判断される場合があります。
留学生の在留資格は原則就労が認められませんが、資格外活動許可を得ることで、一定の条件下ならパート・アルバイトなどが可能です。
しかし、あくまでも学業を目的とした在留資格である以上、次のような状況では取消事由に該当する恐れがあります。
- 正当な理由なく学校の授業を長期間欠席している
- パート・アルバイトに専念し、学業をおろそかにしている
- 退学から3ヵ月が経過しても、在留資格の変更手続きを行わず日本に滞在している
外国人留学生を雇用する際は、資格外活動許可の範囲内(労働時間が週28時間以内、長期休暇中は1日8時間以内)で働いてもらわなければなりません。
学業に支障が出ないよう企業側で労働時間を管理するとともに、留学生の学校生活に問題や変化がないかどうかも定期的に確認しましょう。
雇用している外国人に取消事由該当が疑われた場合の対応
自社で受け入れている外国人が在留資格の取消事由を疑われた場合、企業にはどのような対応が求められるのでしょうか。
適切な対応を取ることで、早期の問題解決をめざせるだけでなく、外国人の在留資格取消しを回避できる可能性もあります。
まずは事情を確認する
外国人のもとに意見聴取通知書が届き、在留資格取消事由の疑いが発覚した場合、企業がまず行うべきは、本人から詳しい事情を聞くことです。
状況をより正確に把握するためにも、事情聴取の際は以下の4点に注意しましょう。
- プライバシーに配慮した場所で話を聞く
- 外国人本人が安心して話せるよう、非難めいた態度を取らない
- 事実関係を客観的に確認する
- 必要に応じて通訳を用意し、認識の齟齬を防ぐ
事情を聞くなかで、致し方のない正当な理由や誤解があったと判明する可能性もあります。
一方で、失踪による不法滞在者など違法性が明らかな外国人の場合、会社側も不法就労助長罪に問われかねません。
地方出入国在留管理局や専門家に相談するほか、出頭をうながすなど、慎重な対応を検討してください。
正当な理由があれば取消しを回避できる
在留資格の取消事由に対して、正当な理由を証明できれば、取消しを回避できる可能性があります。
例えば、配偶者の在留資格に該当する活動を行えない外国人の場合、正当性を認められるのは次のようなケースです。
- 配偶者からの暴力(DV)がある場合
- 配偶者とは別居中だが、子どもの養育などやむを得ない事情で生計を同一にしている場合
- 本国にいる親族の傷病などの事情により、再入国許可を得て長期間の出国をしている場合
- 離婚調停または離婚訴訟中の場合
これらの正当な理由を主張できるのが意見聴取の場ですが、客観的な証拠や資料の提出が求められ、口頭の説明だけでは不十分です。
外国人を受け入れている企業は、本人に代わって必要書類を用意したり、専門家を紹介したりといったサポートを行い、早期の問題解決に向けて協力しましょう。
雇用する外国人の在留資格が取消しにならないよう会社側も管理しよう
在留資格の取消事由は、日本で就労する外国人と受け入れ企業の双方に関わる問題です。
失踪外国人の不法就労などが発覚すれば、企業側も罪に問われる可能性があり、「事情を知らなかった」では済まされません。
外国人の在留資格や活動内容が適切か定期的に確認し、手続きが必要なときには期限内に申請を行うよう、うながすことが重要です。
万が一、雇用している外国人が取消事由への該当を疑われた場合、まずは本人から事情を聞いてみてください。
正当な理由を証明できるようであれば、在留資格の取消しは回避できます。
証拠となる資料の用意や専門家の紹介など、企業側にできるサポートを提供し、問題の早期解決と外国人の雇用継続をめざしましょう。






